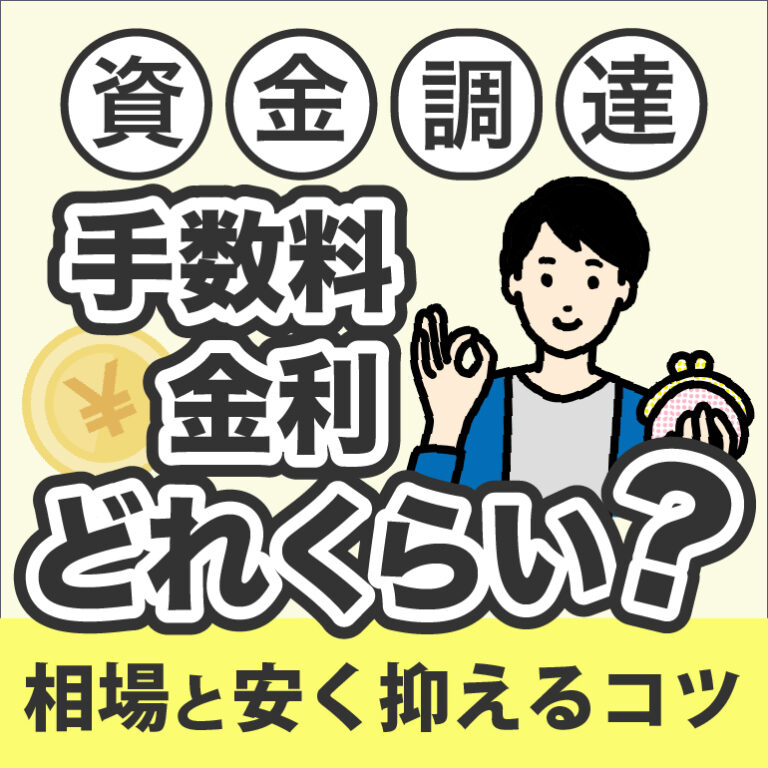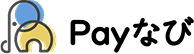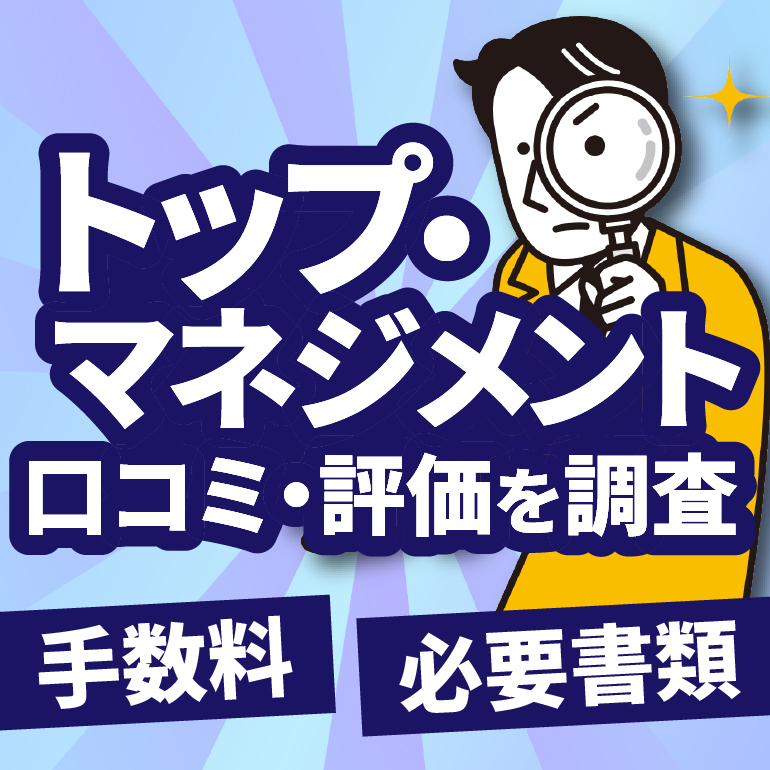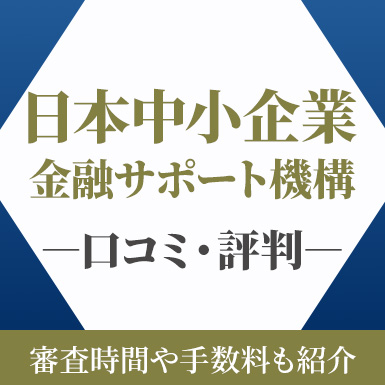事業の資金調達を行う際に気になる手数料や金利。これらの資金調達コストは、融資やファクタリングといった調達方法によって、種類や相場が大きく異なるため、正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、融資や出資、ファクタリングといった調達方法ごとに、どのような手数料がかかるのか、種類と費用相場を比較・解説します。手数料を安く抑えるためのコツも紹介しているので、ぜひ最後までご一読ください。
資金調達方法別の手数料と費用相場を比較
資金調達の手数料や金利は、どの方法を選ぶかで異なります。ここでは、6つの調達方法について、それぞれの手数料の種類と具体的な費用相場を見ていきましょう。
1. 融資
融資は、金融機関に事業資金を借り入れ、利息とともに返済していく資金調達方法です。主なコストは金利ですが、その他にも付随する費用があります。
■かかる手数料
金利(利息)、信用保証料、事務手数料、印紙代など
融資の金利は、借り入れる金融機関の種類によって異なります。以下で、代表的な金融機関を、それぞれの特徴とともに見ていきましょう。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、国が100%出資する創業者や中小企業のための金融機関です。営利を第一目的としておらず、低い金利で利用できる制度が充実しています。
その中でも新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方や、事業開始後おおむね7年以内の方を対象とした融資制度です。
<新規開業・スタートアップ支援資金>
| 融資の条件 | 基準利率(年利) |
|---|---|
| 無担保で、税務申告を2期終えている場合 | 2.70% ~ 4.20% |
| 無担保で、税務申告を2期終えていない場合 | 2.80% ~ 4.30% |
| 有担保で融資を利用する場合 | 1.70% ~ 3.80% |
※令和7年6月時点
なお、以下に該当する創業者は、基準利率から0.40%〜-0.90%程度低い特別利率が適用される可能性があります。
- 女性、35歳未満、または55歳以上の方
- 廃業歴があり、再挑戦する方
- 認定経営革新等支援機関の指導を受けて事業計画を立てた方 など
制度融資
制度融資は、地方自治体・金融機関・信用保証協会の3者が連携して事業者を支援する融資制度です。信用保証協会が事業者の公的な保証人となることで、金融機関(銀行など)が融資をしやすくなるよう、貸し倒れのリスクをカバーします。
地方自治体は、事業者が支払う金利の一部を補助したり、保証料を負担したりすることで、コストを軽減してくれます。この3者の協力により、事業者は民間の金融機関から、通常よりも有利な条件で融資を受けられる仕組みです。
自治体によって金利や制度内容が異なります。ここでは、東京都の制度融資「創業」を例に見ていきましょう。
| 融資期間 | 融資利率の上限 |
|---|---|
| 3年以内 | 1.85%以内 |
| 3年超5年以内 | 1.95%以内 |
| 5年超7年以内 | 2.15%以内 |
| 7年超 | 2.35%以内 |
メガバンク・地方銀行
メガバンクや地方銀行は、実績のある企業には銀行が直接行う「プロパー融資」を行いますが、一般公開はされていません。創業者や中小企業が主に利用するのは、上記の制度融資か、以下のビジネスローンです。
- 金利相場:1.0%~3.5%(制度融資の場合)
- 信用保証料:0.5% ~ 2.0%(制度融資の場合)
<銀行独自のビジネスローン>
| 金融機関名 | 商品名 | 金利 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | ビジネスローン「融活力」 | 2.1%~9.0% |
| 三井住友銀行 | ビジネスセレクトローン | 2.125%~ |
| みずほ銀行 | みずほスマートビジネスローン | 2.1%~14.0% |
2.ファクタリング
ファクタリングは、売掛債権(請求書)を売却して資金化する方法です。融資ではないため金利はありませんが、買取手数料が発生します。
■かかる手数料
買取手数料、登記費用、印紙代など
また、ファクタリングは売掛先が契約に関与するかどうかによって、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに分けられ、それぞれ手数料の相場が異なります。
- 2社間ファクタリングの手数料相場:8%~18%
- 3社間ファクタリングの手数料相場:2%〜9%
売掛先に知られずに手続きを行う2社間ファクタリングは、リスクが高い分、手数料も高めの設定です。対して、売掛先も含めて手続きを行う3社間ファクタリングは、ファクタリング会社にとって未回収リスクが低いため、手数料が安くなる傾向にあります。
手数料の相場を理解した上で、いくつかの具体的なサービスを見てみましょう。ただし、以下に示す手数料は、多くの場合最低手数料率であり、実際の適用手数料は審査によって変動する点にご注意ください。
| サービス名 | 手数料 |
|---|---|
| ビートレーディング | 2.0%~ |
| QuQuMo | 1.0%~14.8% |
| 日本中小企業金融サポート機構 | 1.5%~ |
ファクタリング利用の手数料はいくら?相場・内訳や費用を安く抑える方法
3. 出資(VC、エンジェル投資家)
出資は、ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家といった投資家から、事業の成長性を期待して資金提供を受ける方法です。融資と違い、返済義務や金利の支払いはありません。
ただし、その見返りとして自社の株式の一部を渡すことになります。これは、会社の所有権や、将来得られる利益の一部を手放すことを意味し、融資の金利とは全く性質の異なる、エクイティファイナンス特有のコストといえます。
また、契約時にはFA(フィナンシャル・アドバイザー)や弁護士への専門家報酬も必要です。
4. 補助金・助成金
補助金・助成金は、国や地方自治体が提供する返済不要のお金です。資金提供元に支払う手数料はありません。
ただし、申請手続きが複雑であるため、行政書士やコンサルタントに依頼することもあります。その場合の費用は、着手金(数万〜数十万)+成功報酬(採択額の10%〜20%)が相場です。
5.ビジネスローン(ノンバンク)
ビジネスローンは、銀行だけでなく、信販会社や消費者金融などのノンバンクも提供しています。審査が柔軟でスピーディーな分、金利は高めに設定されています。
■かかる手数料
金利(利息)、事務手数料、印紙代など
銀行や公庫からの融資が難しい場合や、緊急で資金が必要な場合に、ノンバンクのビジネスローンは有効な選択肢となります。以下で、代表的なサービスをいくつか見てみましょう。
| サービス名 | 金利 |
|---|---|
| AGビジネスサポート | 3.1%~18.0% |
| アクトウィル | 7.5%~15.0% |
| キャレント | 7.8%~18.0% |
法人が低金利で利用できるビジネスローンはある?選び方やポイント、注意点を解説
6. クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人から資金を調達する方法です。
クラウドファンディングを行うためには、CAMPFIREやMakuakeといった専門のプラットフォーム(サイト)にプロジェクトを掲載し、支援を募るのが一般的です。そのため、プラットフォームを利用するための手数料がかかります。
■かかる手数料
プラットフォーム利用手数料、決済手数料
| プラットフォーム名 | 手数料(決済手数料込み) |
|---|---|
| CAMPFIRE (キャンプファイヤー) | 17% |
| Makuake (マクアケ) | 20% |
| READYFOR (レディーフォー) | 14% |
資金調達の手数料を安く抑えるためのコツ
ここでは、資金調達の手数料を安く抑えるためのコツを4つ紹介します。
1.複数の金融機関・サービスを比較検討する
金融機関やサービスによって金利や手数料は様々です。複数の会社から見積もり(相見積もり)を取ることで、金利や手数料、融資額といった条件を客観的に比較し、自社にとって有利な一社を選ぶことができます。
なお、「Payなび」では、簡単な入力だけで、提携する複数のファクタリング会社から相見積もりを取ることが可能です。一社ずつ連絡する手間を省き、最も良い条件の会社を効率的に見つけられます。
2.金利の低い公的融資(公庫・制度融資)から優先的に検討する
緊急の資金需要でない限り、手数料を最も安く抑えられる可能性が高いのは、日本政策金融公庫や制度融資といった公的融資です。
公的融資は、創業者や中小企業を支えることを目的とした制度もあり、民間金融機関のビジネスローンに比べて、金利が大幅に低く設定されています。審査に時間はかかりますが、返済総額を考えれば、優先的に検討すべき選択肢です。
また、公的融資を受けられたという実績は、将来の銀行取引においても大きなアドバンテージとなります。
3.事業計画書を綿密に作り込み、交渉材料とする
事業計画書を作成する際は、どの項目においても、具体的な数字に落とし込むことが大切です。具体的なデータに基づいた計画は、金融機関の担当者に、事業の現実性と返済能力をイメージさせやすくします。
たとえば、資金使途の説明で「この融資でマーケティングを強化し、売上を大きく伸ばします」と書くだけでは不十分です。
「融資300万円のうち100万円をWeb広告に投下し、顧客単価2万円の新規顧客を50人獲得します。これにより売上が100万円増加します」といったように、具体的な数値目標と、その根拠を示すことで、計画の信頼性は格段に高まるのです。
融資の審査では、事業への想いと同じくらい、こうした具体的な数字に基づいた計画性が求められています。
4.自己資金をできるだけ多く用意し、信用力を高める
自己資金をできるだけ多く用意しましょう。自己資金は、事業のためにどれだけ自分でリスクを取り、計画的に準備を進めてきたかを示す指標です。
自己資金をできるだけ用意しておくことで、その姿勢が担当者に伝わり、信頼性が向上し、より低い金利などの好条件を引き出しやすくなります。
一般的に、創業資金総額の3分の1程度を用意するのが理想です。また、自己資金の割合が多ければその分、金融機関からの借入額自体を圧縮でき、結果として支払う利息の総額も減らすことができます。
資金調達の手数料に関する質問
ここでは、資金調達の手数料に関する質問に回答していきます。
資金調達にかかった手数料は、経費として計上できますか?
金融機関への支払利息や保証料、ファクタリング会社への手数料、専門家への成功報酬など、事業目的の資金調達に直接関連して発生した費用は、法人税法上の「損金」または所得税法上の「必要経費」として扱うことが可能です。
手数料の勘定科目は、何を使えばいいですか?
手数料の種類によって使用する勘定科目が異なります。
<勘定科目例>
- 日本政策金融公庫や銀行のローン金利:支払利息
- 融資の事務手数料、ファクタリング手数料、専門家への成功報酬:支払手数料
- 信用保証協会に支払う保証料:保証料
- 印紙代:租税公課
迷った場合は、顧問税理士などの専門家に確認しましょう。
資金調達を検討する際は、手数料をしっかり把握しましょう!
調達できる金額だけでなく、それに伴う手数料を把握することが大切です。資金調達の種類によって手数料や金利などのコストは異なります。
本記事で解説した費用相場や、手数料を安く抑えるコツを参考に、自社の事業計画と成長戦略に合った、費用対効果の高い資金調達方法を賢く選択してください。