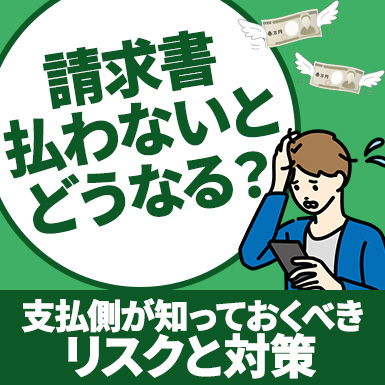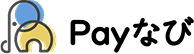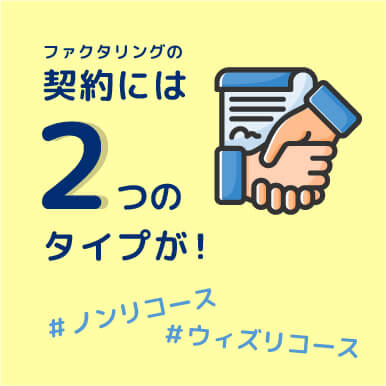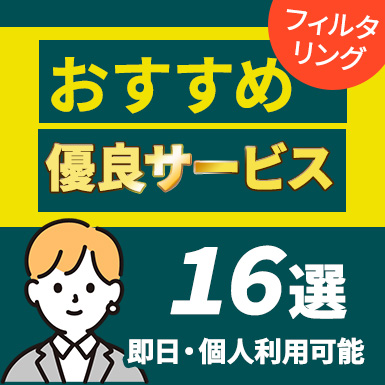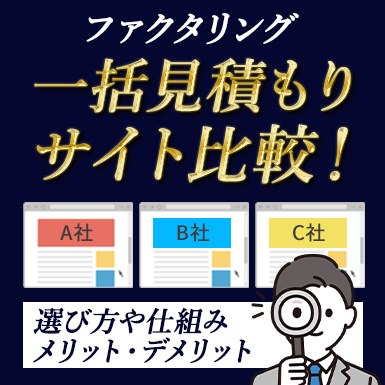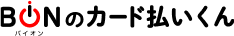請求書の支払いは企業活動において基本中の基本ですが、資金繰りの悪化などでうっかり遅延してしまうケースは少なくありません。
小さな支払い忘れが事業の継続を脅かすこともあるため、請求書管理は経営者にとって決して軽視できない重要な業務です。本記事では、請求書を払わないと発生するリスクや支払いが困難な場合の対処法、未払いを防ぐための管理方法などを紹介します。
請求書を払わないとどうなる?考えられるリスク
資金繰りの悪化などで請求書を払えない状況は、どの企業も避けたいものです。しかし、もし支払いが滞ってしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、請求書を払わないと起こるリスクを紹介します。
遅延損害金が発生する
請求書の支払期日を過ぎると、遅延損害金が発生します。遅延損害金は、契約書で定められた利率、または法定利率に基づいて日割りで計算され、支払いが長引くほど膨らんでいきます。
遅延損害金は以下の計算式で求められます。ここでは、請求書の金額が100万円、遅延損害金の年率10%で、50日間の延滞が発生した例を見てみましょう。
| 債務額 × 遅延損害金利率 × 延滞日数 ÷ 365 = 遅延損害金 100万円 × 10% × 50日 ÷ 365日 =13,698円 |
このように請求書を払わないと、本来の支払額より多くの出費を強いられることになり、財務状況をさらに圧迫します。
督促対応が行われる
支払いが遅れると、相手企業からの督促対応が始まります。最初は電話やメールでの穏やかな確認からスタートしますが、滞納期間が長くなるにつれて、督促状の送付や内容証明郵便での通知など、対応は次第に厳しさを増していきます。
また、これらの督促に対応するための時間や人的コストも無視できません。担当者が督促の電話対応に追われると、本来の業務に集中できなくなり、企業活動全体に支障をきたすことにもなりかねません。
法的措置を取られる
支払い遅延が長期化すると、取引先は法的措置に踏み切る可能性があります。
少額訴訟や支払督促の申立て、通常の民事訴訟などの手続きが進むと、裁判所から支払命令が出されます。従わない場合は財産の差し押さえといった強制執行に発展することもあるでしょう。
また、法的措置に対応するための弁護士費用や訴訟費用、さらには和解金などの追加コストも発生します。
取引先からの信用を失う
請求書の未払いは、何よりも取引先からの信用を大きく損なう行為です。
一度信用を失うと、取引停止になったり、次回からの取引条件が厳しくなったりします。たとえば、今までの掛け取引から現金払いや前払いを要求されるようになると、資金繰りはさらに苦しくなってしまいます。
また、業界内で「支払いの悪い企業」という評判が広まれば、新規取引先の開拓も難しくなり、ビジネスチャンスを失うことにもつながります。SNSが発達した現代では、こうした悪評は想像以上のスピードで広がることを覚えておきましょう。
請求書が来ない場合の支払い義務はある?
取引を行ったにもかかわらず、請求書が届かないケースは実務でよく起こります。取引先の請求書処理が適切に行われていなかったり、郵送の場合に宛先や住所が間違っていたりと、相手側のミスで請求書が届かないことがあるのです。
しかし「請求書が来ていないから支払わなくていい」というわけにはいきません。請求書が来ない場合でも、当然支払い義務はあります。
商品やサービスの提供を受けた時点で支払い義務は発生しており、請求書はあくまで支払い内容を確認するための手段に過ぎないからです。
ただし、未払いの債権には時効があり、民法の規定により支払期日の翌日から5年が経過すると消滅時効となります。以下の記事では、売掛債権の時効について解説しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください。
売掛債権の時効はいつまで?未回収リスクや債権回収を行う方法を解説
請求書の支払いが難しい場合の対応方法
予想外の出費が重なって請求書の支払いが難しくなることは、どんな企業でも起こりうる問題です。ここでは、支払いが難しい場合の対応策を紹介します。
早い段階で取引先に相談する
請求書の支払いが難しいとわかった時点で、すぐに取引先に状況を正直に伝えましょう。
期日直前や期日を過ぎてからの連絡では、相手の信頼を大きく損ねてしまいます。早めに連絡すれば、取引先も対応する時間的余裕ができ、柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。
支払条件を交渉する
取引先に状況を説明した上で、支払条件の変更を交渉してみましょう。一括での支払いが難しい場合は、分割払いを提案するのも一つの方法です。
たとえば「まず今月末に半額を支払い、残りは来月末に支払う」といった具体的な提案をすれば、相手も検討しやすくなります。
また、支払期日の延長を交渉することも可能です。その際、延長期間の遅延損害金の支払いも一緒に提案すると、より誠意が伝わりやすくなるでしょう。
交渉は電話やメールよりも、対面やオンライン会議で行う方が効果的です。誠実な態度で臨み、一方的なお願いにならないよう気をつけましょう。
資金調達を検討する
支払期日までに資金を確保するため、様々な資金調達方法を検討することも大切です。代表的な方法としては融資などが挙げられますが、急ぎの場合はファクタリングを活用するのも手です。
ファクタリングを利用すれば、自社の売掛債権を早期に現金化できます。通常の回収より早く資金を得られるため、急な支払いにも対応できるでしょう。
ただし、ファクタリングには手数料がかかるため、コストを考慮した上で判断する必要があります。自社の状況に合った資金調達方法を探しましょう。
請求書カード払いを活用する
最近では、請求書の支払いを振込からクレジットカードで変更できる「請求書カード払い」のサービスも増えています。
請求書カード払いの「カード払いくん」では、クレジットカードの利用枠内で支払いを行い、実際の引き落としを最大60日後に延ばすことができます。資金繰りが一時的に厳しい場合の息継ぎ策として効果的です。
請求書の未払いが起こる原因
請求書の支払いが滞ってしまう状況は、大企業から中小企業まで、規模に関わらず発生することがあります。請求書の未払いが起こる原因は以下のとおりです。
- 請求書を紛失して放置してしまった
- 請求書を受け取った人が、経理担当者に渡しそびれてしまった
- 入金期日を管理できていない
- 急な支払いが同時に発生して資金が足りない
こうした問題を防ぐためには、請求書の受領から支払いまでの流れを明確にし、社内での情報共有の仕組みを整えることが重要です。
また、キャッシュフローの予測や資金繰り計画をしっかり立てることで、突発的な支払い不能に陥るリスクを減らすことができるでしょう。
請求書が払えない状況を防ぐための管理方法
ここでは、請求書が払えない状況を未然に防ぐための方法を紹介します。
請求書管理システムを活用する
請求書の支払い漏れや遅延を防ぐには、請求書管理システムを導入するのも1つの方法です。クラウド型の請求書管理システムを使えば、受け取った請求書をデータとして一元管理できるため、紛失や処理漏れのリスクが減ります。
多くのシステムには、支払期日が近づくとアラートが表示される機能があり、担当者に自動で通知することも可能です。「あと3日で支払期日です」といった通知があれば、うっかり忘れることもなくなるでしょう。
支払いスケジュールを可視化する
請求書の支払いを確実に行うためには、支払いスケジュールの可視化が重要です。月間・四半期ごとの支払いカレンダーを作成し、いつ、どの取引先に、いくらの支払いが発生するかを一目で把握できるようにしましょう。
固定費(家賃や人件費など)と変動費(仕入れや外注費など)を分けて管理することで、資金繰りの予測精度も高まります。
また、入金予定も同じカレンダーに記載しておけば、資金の出入りバランスが視覚的に確認でき、資金ショートのリスクを早期に発見できます。
請求書の未払いを防ぐなら「カード払いくん」が便利
資金繰りが厳しい時期でも、請求書の支払いを確実に行いたい事業者におすすめなのが「カード払いくん」です。
カード払いくんは、通常は銀行振込で支払う請求書の支払いをクレジットカードで決済できるサービスです。請求書の支払いを最大60日間先延ばすことができます。
取引先には通常の銀行振込と同じように入金されるため、カード払いを利用していることは相手に知られません。
利用開始もとてもスピーディで、WEB上で最短60秒から手続きができます。審査や複雑な書類提出も必要ないため、「明日までに支払わなければ」という急な資金需要にも柔軟に対応しやすいです。さらに、カード決済によるポイントやマイルも通常通り貯まります。
請求書に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、請求書に関して寄せられた質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
Q1:請求書を紛失した場合、支払いはどうすればよいですか?
請求書を紛失してしまった場合は、すぐに取引先に連絡して再発行を依頼しましょう。多くの企業では請求書をPDFなどの電子データで保管しているため、比較的スムーズに対応してもらえるでしょう。
請求書を紛失したことや支払いの意思があることをはっきり伝え、率直に謝罪することが大切です。また、取引内容や請求書番号が分かれば伝えておくと、取引先が請求書を特定しやすくなります。
Q2:請求書の時効は何年ですか?
請求書に基づく債権(売掛金)の時効は、改正民法により「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方が適用されます。
通常のビジネス取引では、請求書の発行日や支払期日から5年が経過すると時効となる場合が多いです。
ただし、督促状の発送や債務承認があると時効は更新されるため、「放っておけばいつか消える」というものではありません。支払う側は時効を当てにせず、しっかり請求書を払いましょう。
請求書の未払いはリスクが大きい!しっかり管理しましょう
請求書の未払いは、単なる支払い忘れと軽視できない問題です。請求書を払わないと、遅延損害金の発生や取引先との関係悪化、最悪の場合は法的措置による強制執行など、事業継続に影響を及ぼしかねません。
請求書管理システムの活用や支払いスケジュールの可視化など、適切な管理体制を構築することが大切です。資金繰りに不安がある場合は、早めに取引先へ相談したり、「カード払いくん」のようなサービスを活用したりするなど、状況に合わせた対応を検討しましょう。