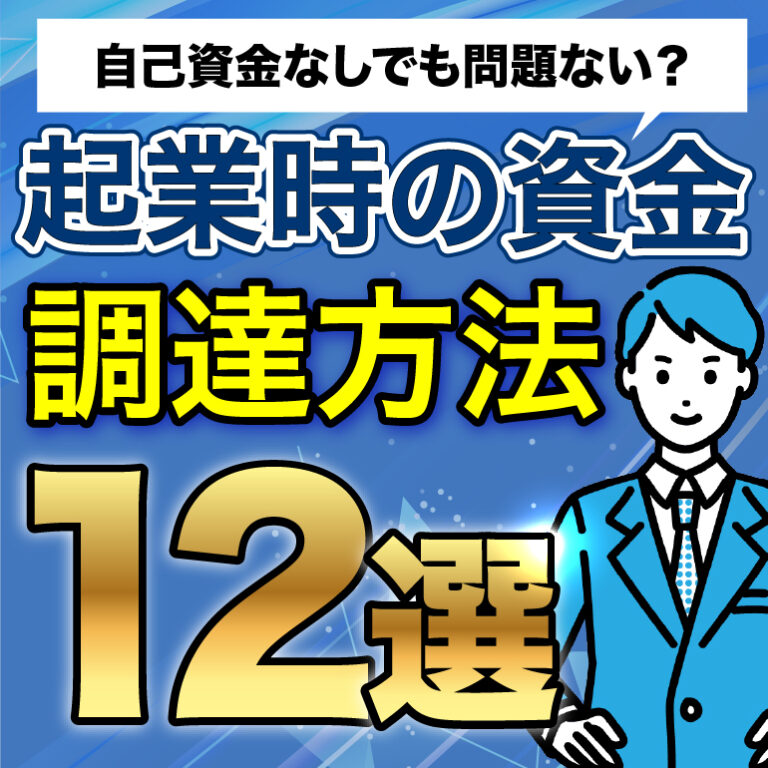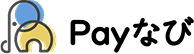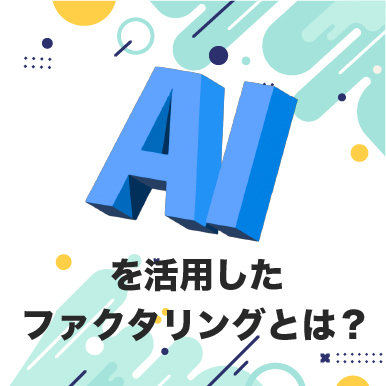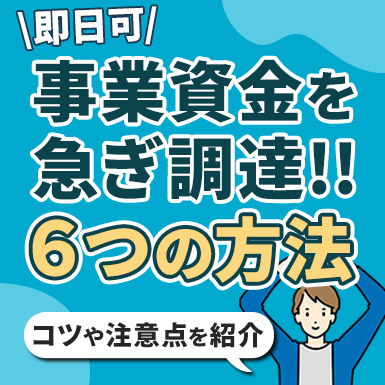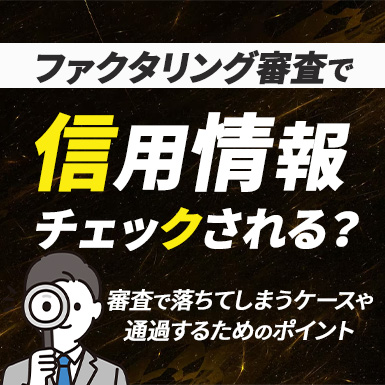事業を立ち上げるためには、当然資金が必要になります。自己資金だけでは足りず、外部からの資金調達が必要になることも少なくありません。
起業を成功させるためには、どのような資金調達の方法があるかを把握し、事業計画にあった手段を準備することが大切です。
この記事では、起業時に活用できる資金調達方法を12種類に分けて、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。自社に合った調達方法の選び方や、資金調達を成功させるための重要なポイントも紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
起業(会社設立)時の資金調達方法
ここでは、起業時に利用できる12種類の資金調達方法について、それぞれの特徴を見ていきましょう。
1.自己資金
起業資金をすべて自己資金でまかなえれば、それに越したことはありません。Web制作やコンサルティングなど、初期費用を抑えたスモールビジネスなら、自己資金だけで十分にスタートできます。
ただし、すべての業種に当てはまるわけではありません。事業を早期にスケールさせたい場合や、初期投資がかさむ業種では、自己資金だけでは不十分なケースがほとんどです。
2.日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫(JFC)は、日本政府が100%出資している金融機関で、中小企業や小規模事業者、創業期の事業者への融資を積極的に行っています。民間の銀行と比べても金利が低く、無担保、無保証人で利用できる制度もあります。
中でも、新規開業・スタートアップ支援資金では、最大7,200万円(うち運転資金は4,800万円)までの融資が可能です。
さらに、女性や35歳未満の若者、55歳以上のシニア、廃業歴のある方の再挑戦を支援する優遇制度もあり、対象者はより有利な条件で融資を受けられる可能性があります。
3.制度融資
制度融資とは、地方自治体・民間の金融機関・信用保証協会の3機関が連携して行う融資制度です。
地方自治体が利子の一部を負担してくれたり、信用保証協会が保証人となったりすることで、創業期の事業者や中小企業が民間の金融機関から融資を受けやすくする仕組みです。
日本政策金融公庫の融資と同様、金利が低いのがメリットです。一方で、審査に関わる機関が多いことから、申し込みから入金までの期間が2〜3ヶ月と長めにかかる点には注意が必要です。
4.補助金・助成金
補助金・助成金は、国や地方自治体が提供している、返済が不要なお金です。各補助金・助成金の要件を満たし、審査に採択されれば、事業資金として活用できます。代表的な補助金を以下にまとめました。
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者の販路開拓(広告宣伝、Webサイト制作など)を支援 |
| ものづくり補助金 | 革新的な製品・サービス開発のための設備投資などを支援 |
| IT導入補助金 | 会計ソフトや受発注システムなどのIT化を支援 |
| 事業再構築補助金 | 新市場への進出や事業転換など、大規模な事業再構築を支援 |
ただし、補助金・助成金は事業実施後に経費を請求する「後払い制」であるため、すぐに資金を調達できるわけではありません。また、審査に通過するためには準備も手間がかかり、採択率も制度によって様々です。
5.クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人から、少額ずつ集める方法です。製品やサービスのアイデアをWebサイト上に公開し、想いやビジョンに共感した支援者から資金を募ります。
また、資金調達だけでなく、市場の反応を見るテストマーケティングや、ファン獲得などの目的で活用できるのもメリットです。
6.信用金庫・地方銀行の融資
信用金庫や地方銀行は、地域に根ざした経営を行っており、地域の事業者に対して親身に相談に乗ってくれる傾向にあります。
事業の数字だけでなく、地域への貢献度や将来の成長性、経営者の人柄といった点も含めて判断してもらえる可能性があります。大手の銀行よりも融資のハードルが低い場合があり、中には創業融資を積極的に行っている地方銀行もあります。
7.ビジネスコンテスト
ビジネスコンテスト(ビジコン)は、事業計画やアイデアを競う大会です。民間の企業や大学、地方自治体などが開催しています。
事業計画やアイデア次第で、賞金として事業資金を得られるほか、投資家やメディアの注目を集められます。資金調達だけでなく、事業のブラッシュアップや人脈形成といった面でもメリットのある方法です。
8.エンジェル投資家
エンジェル投資家は、創業期のスタートアップ企業に資金を提供する個人投資家です。投資家自身の資産を使って、応援したい起業家や事業に直接出資します。
個人であることから、ベンチャーキャピタル(VC)などと比較して、迅速な意思決定が期待できるのがメリットです。
また、元経営者や成功した起業家も多く、単なる資金提供だけでなく、自身の経験に基づく経営アドバイスや人脈の紹介といった、ハンズオン支援を受けられる場合もあります。
9.ベンチャーキャピタル(VC)
ベンチャーキャピタル(VC)は、将来的に高い成長が見込まれる未上場企業に出資する投資会社です。数千万円から数億円といった大規模な資金調達が可能で、企業の急成長を目的とする場合に活用されます。
ただし、VCは出資の見返りとして企業の株式を取得するため、経営の自由度が一部制限される可能性があります。
10.ファクタリング
ファクタリングは、既に入金待ちの状態にある売掛債権(請求書)をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、期日前に現金化するサービスです。
融資とは異なり、借入扱いにはなりません。入金スピードが早く、最短で即日できるケースもあります。
起業直後でも、例えば個人事業主から法人成りした場合など、既に取引実績と売掛債権があれば、それを元に運転資金を調達できます。
ファクタリングとは?仕組みやメリット、利用が向いているケースをわかりやすく解説
11.ビジネスローン
ビジネスローンは、消費者金融や信販会社などのノンバンクが提供する事業者向けのローンです。
銀行融資に比べて審査スピードが非常に速く、最短即日で借入できる場合もありますが、その分金利は高めです。緊急でつなぎ資金が必要な場合など、短期的に利用する場合に向いています。
法人が低金利で利用できるビジネスローンはある?選び方やポイント、注意点を解説
12.家族・友人からの借入
親族や友人・知人から資金を借りるのも資金調達方法の一つです。金利や返済条件を柔軟に設定できる可能性がありますが、関係性の悪化を招くリスクも伴います。
必ず借用書を作成し、返済計画を明確にするなど、後々の金銭トラブルを避けるための対策を徹底しましょう。
起業に必要な資金はどれくらい?
日本政策金融公庫が2024年11月に公開した「2024年度新規開業実態調査」によると、開業費用の平均値は985万円でした。ただし、これは一部の高額なケースに影響されている数字でもあり、より実態に近い中央値は580万円となっています。
実際に、開業費用が500万円未満だった方の割合は合わせて41.1%(250万円未満が20.1%、250~500万円未満が21.0%)と最も高く、多くの人が比較的少額から事業を始めていることがわかります。
自己資金なしでも起業できる?
自己資金なしで起業することはできますが、現実的には非常に厳しいといえます。
以前、日本政策金融公庫の創業融資には「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」という要件がありましたが、この要件は現在撤廃されています。
とはいえ、だからといって自己資金の重要性がなくなったわけではありません。融資の審査では、事業計画の妥当性だけでなく、創業者自身の「本気度」も厳しく見られます。
コツコツと自己資金を貯めてきた点は、事業に対する情熱と覚悟を示すと同時に、申込者の返済能力を評価する上での重要な判断基準となります。そのため、自己資金はなるべく多いに越したことはないといえるでしょう。
自社に適した資金調達方法の選び方
ここでは、自社に適した資金調達方法を選ぶための7つの判断軸を紹介します。
資金の必要額で選ぶ
事業に「いくら必要なのか」という金額規模で、選択肢はある程度絞られます。
- 少額(〜100万円):自己資金/クラウドファンディング(購入型)/知人からの借入
- 中額(100万〜1,000万円):日本政策金融公庫/制度融資/補助金
- 高額(1,000万円〜):VC/エンジェル投資/銀行融資
返済の有無で選ぶ
調達した資金を「返済する必要があるかないか」は、将来のキャッシュフローに影響する重要な判断軸です。
- 返済したくない場合→補助金・助成金/クラウドファンディング(寄付型・購入型)/出資
- 返済は可能な場合→融資/ファクタリング/ビジネスローン
資金調達のスピードで選ぶ
「いつまでに資金が必要か」という緊急度によっても、選ぶべき方法は異なります。
- 今すぐ必要→ノンバンク融資/ファクタリング
- 1〜3ヶ月以内でOK→公庫融資/制度融資/補助金(申請タイミングによる)
信用力で選ぶ
創業直後は、会社の信用力(実績)がまだありません。自身の状況に合わせて選択肢を考えましょう。
- 信用力に不安がある(創業直後など)→日本政策金融公庫/クラウドファンディング/自己資金/ファクタリング
- 信用力がある→銀行融資/VC/保証付き融資
事業フェーズで選ぶ
会社の成長段階(事業フェーズ)によって、適した資金調達方法は変わっていきます。
- アイデア段階→クラウドファンディング/ビジコン
- 初期試験・PoC→補助金/エンジェル投資
- スケール段階→VC/銀行融資/シリーズA以降の出資
経営への関与の程度で選ぶ
資金だけでなく、経営に関するアドバイスやサポートを求めるかどうかも、重要な判断基準です。
- 経営に口出しされたくない→自己資金/融資/補助金
- アドバイスや経営支援がほしい→エンジェル投資/VC
資金の使い道で選ぶ
調達したい資金の使い道(使途)によって、相性の良い制度があります。
- 設備投資→日本政策金融公庫/制度融資/ものづくり補助金
- 運転資金(日々の仕入・家賃・光熱費・人件費など)→ファクタリング(すでに事業が動いている場合)/雇用助成金(人件費用)
- 販促広告→小規模事業者持続化補助金/クラウドファンディング
起業時に資金調達を検討する際のポイント
ここでは、起業時に資金調達を検討する際に、事前に押さえておくべきポイントを8つ紹介します。
起業資金の用途と必要な金額を明確にする
「何に、いくら必要なのか」を具体的に書き出しましょう。起業資金の用途と必要な金額を明確にすることで、適した資金調達方法が分かり、事業計画の説得力も増します。
自己資金を用意する
自己資金は事業への「本気度」の証明です。自己資金の有無や割合が審査結果に影響することが多いため、全額でなくとも、一定額は必ず用意しましょう。
必要資金の3割程度の自己資金が目安です。ただし、事業の内容や規模によって柔軟に判断されることもあります。必要資金を項目ごとに整理し、その中で自己資金で賄える部分を明確にしておくことが重要です。
事業計画書を作り込む
事業計画書は、いわゆるプレゼン資料です。創業時の融資や出資の審査では、提出する事業計画書の内容が結果を大きく左右します。
事業のビジョンや市場分析、収支計画、成長戦略などを、誰が読んでも理解できるよう具体的に、かつ情熱をもって記載しましょう。
信用情報や過去の経歴を整理する
公庫や銀行からの融資では、創業者個人の信用情報(クレジットカードやローンの延滞履歴など)も確認されます。
事前に自身の信用情報を確認し、もし懸念があれば、その理由を説明できるように準備しておきましょう。
返済計画(キャッシュフロー)を具体的にシミュレーションする
融資を受ける場合は、返済が始まっても事業の資金繰りが回るのか、具体的なキャッシュフロー計画を立てることが不可欠です。楽観的すぎず、悲観的すぎない、現実的なシミュレーションを行いましょう。
出資による経営権の変動リスクを把握する
VCやエンジェル投資家から出資を受ける際は、株式を渡すことになります。渡す株式の割合によっては、経営の重要な意思決定に外部の意見が大きく影響する可能性があることを留意しておきましょう。
法人設立のタイミングを調整する
融資や補助金の中には、「創業前」や「設立後一定期間内」でないと申請できないものがあります。利用したい制度の要件を事前に調べ、法人を設立するタイミングを慎重に判断しましょう。
資金調達の期間・タイミングを考慮する
公的融資や補助金は、申請から入金まで数ヶ月かかるのが一般的です。資金が底をつく直前に慌てて申し込んでも間に合いません。
事業計画に基づき、常に数ヶ月先を見越して、余裕を持ったスケジュールで動き出すことが重要です。
複数の資金調達を組み合わせる
資金調達を検討する際、一つの方法に固執する必要はありません。ひとつの調達手段に頼りすぎると、万が一審査に落ちたときや想定より資金が足りなくなったときに立ち行かなくなります。
こうした事態を防ぐためにも、複数の資金調達方法を同時に、あるいは段階的に検討・申請しておくことが賢明です。
起業の資金調達に関するまとめ
起業時の資金調達の本来の目的は、事業を軌道に乗せ、持続的な成長を実現することです。
融資、補助金、出資といった多様な選択肢の中から、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の事業計画やフェーズに最適な手段は何かを考えることが非常に大切です。自社に合った方法を選択し、企業の着実な成長につなげていきましょう。